完全に眠ってしまうって本当?鎮静剤を使った内視鏡
2022.12.13

近年の内視鏡装置の進歩、またそれを用いる我々専門医の手技向上は目覚しいものがあります。しかし、未だ胃カメラや大腸内視鏡は決して「楽な検査」ではありません。そのような中、鎮静剤を使用した内視鏡のニーズは年々高まっています。令和3年度の当院の場合、胃カメラでは9%、大腸内視鏡では27%の患者さまが鎮静剤を使用して内視鏡を受けられています。以前のように患者さまに我慢を強いる時代ではなく、患者さまの価値観を尊重し、希望の多様性に添わなければいけない時代です。鎮静剤を使用した内視鏡という選択肢は世界的な潮流といえます。
|適切な鎮静レベルとは?
鎮静剤を注射するとウトウトと眠ったような状態で内視鏡が受けられます。よく患者さまに「先生!完全に眠ってしまうのですよね?」と聞かれます。答えは「Yes」でもあり「No」でもあります。ガイドラインでは「意識下鎮静」が適切な鎮静レベルとして推奨されています。これは刺激を加えないとウトウトと眠っていますが、声をかけたり、体に触れたりすると目を開けて反応するレベルです。これを聞くと心配になる患者さまが時々いらっしゃいます。しかし、過剰な鎮静は、呼吸が弱くなったり、血圧が低下したり危険を伴います。また、この鎮静レベルでも患者さまの満足度は非常に高いというエビデンスもあります。当院ではミダゾラムという鎮静剤を使用しています。この薬には健忘作用という検査中の嫌なことを忘れてしまう効果があります。このため、実際は検査中の事をあまり覚えていない患者さまがほとんどです。
|鎮静剤を使用した内視鏡を安全に行うために
鎮静剤を使用した内視鏡は安全に実施されなければいけません。検査前の問診で患者さまから安全に実施するための情報を得ることはとても大切です。内視鏡の鎮静剤には新旧色々なものがあります。その中で、当院で使用するミダゾラムは、効果出現・消失が早いこと、安全治療域の幅が広く余裕があることより使いやすい薬剤です。内視鏡の鎮静剤としての歴史も長く、現在でも広く使用されています。フルマゼニルとうい拮抗薬(鎮静剤が効き過ぎたときにその効果を打ち消す薬)が存在するのも長所で、当院にも常備しています。検査中はベッドサイドモニターで呼吸状態(血中酸素濃度)などを監視しながら行います。当院の検査ベッド(ストレッチャー)には酸素ボンベが搭載されおり、必要時にスムーズに酸素投与が行えます。検査終了後はリカバリールームで1時間程度、状態の観察を行います。
この度、ベッドサイドモニターを最新機種(FUKUDA DENSHI DS-8005F)に更新しました。血圧、心拍数、心電図、血中酸素濃度といった観察する基本的な身体情報は長らく変わりありません。これまで使用していたベッドサイドモニター(COLIN NEXTBP88)は名機で不調もなくまだまだ使用可能なのですが、購入後10年以上が経過し更新することとしました。長期にわたり当院で内視鏡を受ける患者さまを見守ってくれた功績に感謝します。新しいベッドサイドモニターは基本的な機能はこれまでのものと変わりありません。携帯性が向上しており、移動時やリカバリールームでの使用がこれまでより容易になると期待しています。
角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では、今後も引き続き「苦しくない」「安全で」「正確な」内視鏡をめざします。
あなたの脂肪肝、本当に大丈夫ですか?
2022.11.28
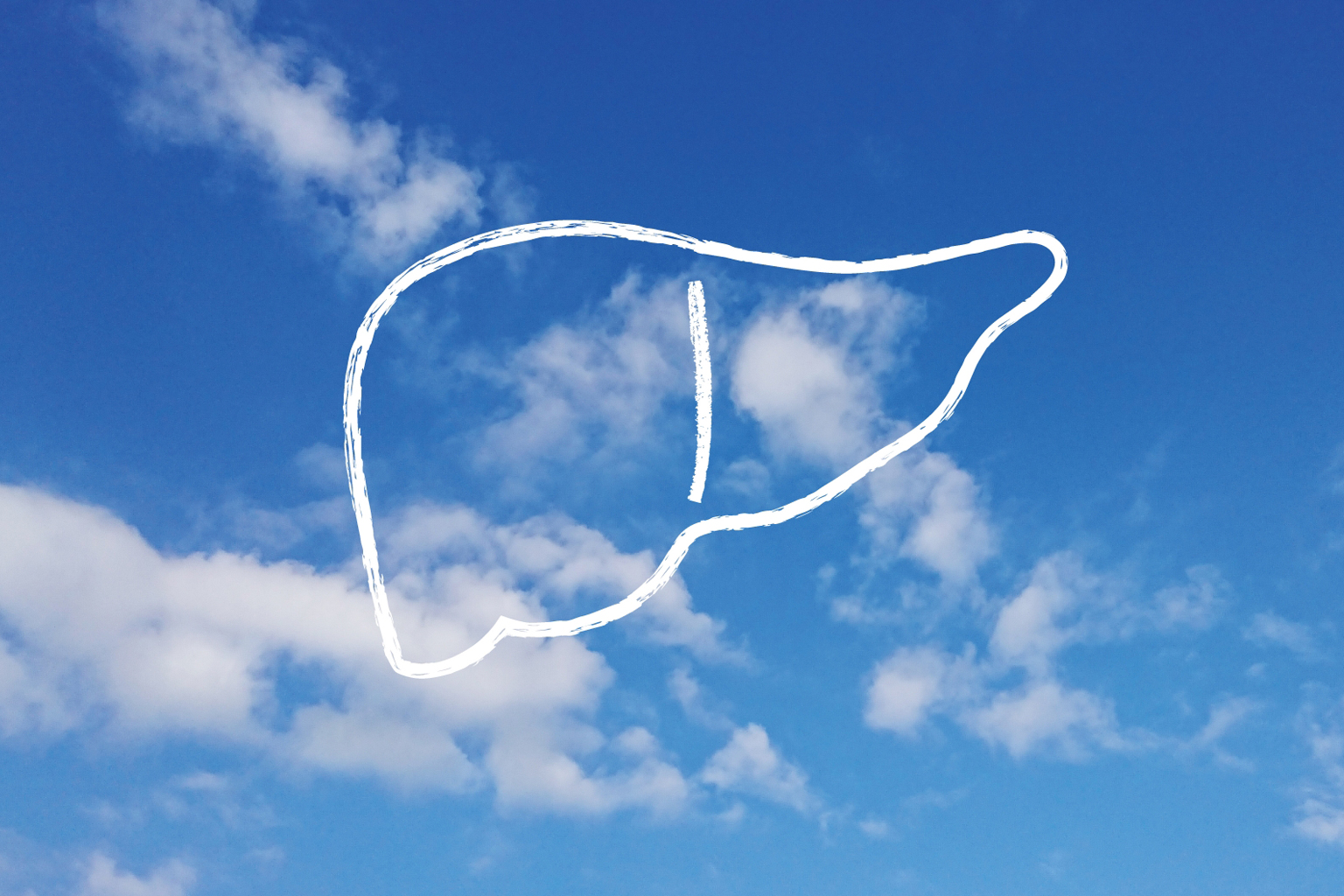
・「脂肪肝」とは?
肝臓に脂肪がたまりフォアグラのような状態になったものを「脂肪肝」といい、いまや日本人の3人に1人が罹患していると言われています。健康診断で指摘されたことがある方も多いのではないでしょうか?
これまで「軽い病気」と考えられてきた脂肪肝ですが、最近になり「決して油断してはいけない病気」であることが分かってきました。
・危険な脂肪肝の存在
お酒が肝臓に悪いことはよく知られていますが、日本人が脂肪肝になる原因の多くは「食べ過ぎ」です。
お酒をたくさん飲まない人の脂肪肝を「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」といいます。NAFLDの患者では狭心症や心筋梗塞が多いことが近年の研究で知られており、生活習慣病の温床として認知されるようになりました。
NAFLDには下記2つのタイプがあります。
■症状が軽く改善しやすい単純性脂肪肝(NAFL)
■重症の非アルコール性脂肪肝炎(NASH)
特に後者のNASHは、放置すると肝硬変や肝臓癌へ進行します。NAFLも放置するとNASHに進行することがあります。
脂肪肝の人すべてが重症化するわけではありませんが、早期に診断して原因となる生活習慣や肥満を改善し、慎重に経過観察することが大切です。
・重症化する危険性のある脂肪肝(NASH)を診断するには?
肝臓は「沈黙の臓器」と言われているため、症状からは診断できません。また、症状があるときは既に進行している可能性があります。
代表的な肝臓の病気で知られているB型・C型肝炎は血液検査をすれば簡単に診断できます。しかし脂肪肝(NASH)では「これを調べれば間違いなく診断できる」という血液検査は現時点では存在しません。
よって、複数の血液検査や画像診断を駆使し、その解釈で病気の存在を疑う医師のテクニックが不可欠です。
こんなに身近にありふれた病気であるにもかかわらず、脂肪肝(NASH)の診断はとても難しいのです。
・何とか早期に脂肪肝(NASH)を発見できる診断方法は無いでしょうか?
完璧ではないのですが、ひとつの方法として挙げられるのは「FIB4インデックス」というものです。
これは肝臓の病気の進行度を予測する計算式のことで、年齢・血小板値・肝機能(AST、ALT)といった、健康診断で一般的に行われている検査項目を基に導き出されます。「1.30以上」が脂肪肝(NASH)を疑うひとつの指標です。
日本肝臓学会のホームページにアクセスして該当項目の検査結果を入力すれば、誰でも値が計算できます。
他に挙げられる簡単な診断方法としては、血小板値の確認があります。
一般に血小板の基準値は15万~35万個くらいです。ほとんどの肝臓の病気は、進行すると徐々にこの血小板値が低下していきます。そして脂肪肝(NASH)では、C型肝炎など他の肝臓の病気に比べ、症状が進行しても血小板値の低下が緩やかであると言われています。
よって、より早期に脂肪肝(NASH)を発見するためには、血小板値の正常範囲内である20万個を切る頃から疑ってもよいと思います。血小板の検査結果が正常値の範囲内であっても、実際の数値をしっかりとご確認ください。
健康診断の結果を今一度ご確認頂き、脂肪肝に関して何か気になることがありましたら遠慮なくご相談ください。
令和3年度 当院における大腸内視検査(大腸カメラ)の実施状況
2022.04.14

昨年度の当院の大腸内視鏡実施状況に関してご報告します。当院で大腸内視鏡検査を受けられる患者さまの参考になれば幸いです。
・実施した数
| 令和3年度 | 184人 |
| 令和2年度 | 156人 |
| 令和1年度 | 136人 |
| 平成30年度 | 162人 |
・実施した大腸内視鏡の詳細
| 全大腸内視鏡検査 | 118人(64%) |
| 鎮静剤を使用した(眠ってする)全大腸内視鏡検査 | 51人(27%) |
| S状結腸内視鏡* | 15人(8%) |
・主な検査の目的
| 血便の原因を調べるため | 30人(16%) |
| 腹痛、下痢、便秘などの症状の原因を調べるため | 49人(26%) |
| 前回の大腸カメラで指摘された病変の経過観察のため | 23人(12%) |
| 健康診断(便潜血反応など)で異常を指摘されたため | 63人(34%) |
・診断した大腸の病気で特筆すべきもの
| 進行大腸癌 | 1人 |
| 早期大腸癌 | 3人 |
| 大腸ポリープ | 70人 |
| 潰瘍性大腸炎・クローン病 | 4人 |
| 虚血性腸炎 | 1人 |
| アメーバー性腸炎 | 1人 |
・大腸ポリープの転帰
| 当院でポリープを治療切除 | 6人 |
| 高次医療機関にポリープの診断治療を依頼 | 10人 |
| 経過観察 | 54人 |
≪総括≫
コロナウィルス流行に伴う病院への受診控えが問題となっていますが、昨年度の当院での大腸内視鏡検査の実施数は例年並みといった状況です。
患者さまの苦痛の少ない内視鏡へのニーズの高まりにより、鎮静剤を使用した大腸内視鏡の割合は3割程度と年々増加傾向にあります。クリニックを移転後、鎮静剤を使用した内視鏡を行えるよう環境整備したこともあり、最近では私自身も大腸内視鏡に対する不安感の強い患者さまへは積極的に鎮静剤の使用を勧めるようになりました。まずは、大腸内視鏡検査を受けていただき、しっかりと診断を行うことが大切だと考えています。
大腸ポリープに関しては、昨年度当院では6人の患者さまの治療を行いました。すべて偶発症なく無事に完了しています。技術的に難しい患者さまに関しては東北大学病院、仙台医療センター、東北医科薬科大学病院、仙台市立病院に治療を依頼しました。
昨年、無症状のアメーバー性腸炎を経験しました。アメーバー性腸炎は赤痢アメーバに汚染されたものを摂取することにより発症し、多くは腹痛、下痢、血便といった症状を呈します。私が当院に着任してから3人目のアメーバー性腸炎の患者さまですが、これまではいずれも症状のある患者さまでした。しかしながら、今回のように便潜血陽性のため内視鏡を行い発見されるケースが0.1%の頻度であると国内で報告されています。症状ない患者さまの大腸内視鏡検査においても留意しておかなければいけません。
*S状結腸内視鏡検査:
通常の大腸カメラは下剤を内服して腸を空っぽにしてから内視鏡を挿入し肛門から盲腸まで全ての大腸を観察します。よって、全大腸内視鏡検査ともいいます。S状結腸内視鏡は肛門から近い部分の大腸(S状結腸~下行結腸まで)のみ観察します。当院では血便の患者さまが来院したとき、浣腸や下剤を使用せずに当日緊急で行っています。下剤を内服しないため、また奥まで内視鏡を挿入しないため、安全に行うことができます。また、出血の程度が分かるため緊急性の有無の判断に役立ちます。血便の場合は肛門から近い大腸に病気が存在することが多いため、出血の原因が診断できることもあります。しかしながら、下剤を内服していないため便や血液が邪魔をして詳細な観察ができません。また、全ての大腸を観察していないのが不十分です。よって、多くの場合、後日下剤を内服して全大腸内視鏡を行っています。その前の偵察のようなものです。
令和3年度 当院における上部内視検査(胃カメラ)の実施状況
2022.04.14

昨年度の当院の胃カメラの実施状況に関してご報告します。当院で胃カメラを受けられる患者さまの参考になれば幸いです。
・実施した人数
| 令和3年度 | 528人 |
| 令和2年度 | 555人 |
| 令和1年度 | 570人 |
| 平成30年度 | 540人 |
・検査の種類
| 経口内視鏡(口からの胃カメラ) | 286人(54%) |
| 経鼻内視鏡(鼻からの胃カメラ) | 192人(36%) |
| 鎮静剤を使用した上部内視鏡(眠ってする胃カメラ) | 50人(9%) |
・主な検査の目的
| 胃の痛み・胸やけなど症状の原因を調べるため | 200人(38%) |
| 前回の胃カメラで指摘された病変の経過観察のため | 96人(18%) |
| 健康診断(バリウムなど)で異常を指摘されたため | 54人(10%) |
| 仙台市胃がん内視鏡検診 | 140人(26%) |
・診断した胃の病気で特筆すべきもの
| 早期胃癌 | 6人 |
| 未治療のピロリ菌による胃炎 | 54人 |
| 治療を必要とする逆流性食道炎 | 8人 |
| 胃・十二指腸潰瘍 | 5人 |
| 胃粘膜下腫瘍 | 15人 |
| 胃腺腫 | 3人 |
| 食道胃静脈瘤 | 2人 |
| アニサキス症 | 1人 |
| 薬剤性食道炎 | 1人 |
≪総括≫
昨年度の胃カメラの受診者は例年より若干少なめでした。コロナウィルス流行に伴う病院への受診控えが問題となっておりますが、幸い当院では進行胃癌の患者さまはいませんでした。
早期胃癌と診断した患者さまは例年より多かった印象です。昨年、胃カメラを最新機種に更新したこと、開院後24年が経過しかかりつけ患者さまが高齢化してきていることが影響していると推定しています。
衛生環境の向上から国内ではピロリ菌感染者は減少傾向にありますが、当院ではピロリ菌による胃炎の診断は増加傾向にあります。2020年にピロリ菌の診断装置を導入したため、ピロリ菌の診療治療目的に受診される患者さまが増加したためと推定しています。
胃カメラの苦痛軽減のニーズは年々高まっていて、昨年度は半分弱の患者様が経鼻内視鏡や鎮静剤を使用した内視鏡を選択していました。従来の経鼻内視鏡は画質にやや不満がありましたが、最新機種ではこれを克服しているため自信をもってお勧めできるようになりました。苦痛なく精度の高い検査を受けられるように今後も環境を整えていきたいと思います。
昨年度、ダビガトラン(商品名:プラザキサ)による薬剤性食道炎を経験しました。胸やけのある患者さまの原因を調べるため胃カメラを行ったところ、特徴的な食道炎を認めました。ダビガトランを内服していたため、この疾患を疑い他の薬に変更したところ改善しました。ダビガトランは心房細動の患者で血栓予防のために使われる抗凝固薬です。この病気は2012年頃に報告され、当時は話題になりました。近年は他の抗凝固薬がいくつか発売され、ダビガトランを内服している患者さまは減った印象です。しかしながら、いまだ留意しなければいけない病気であると思いました。
胃がんの早期発見・早期治療のため胃内視鏡(胃カメラ)検診を受けましょう!
2021.07.25

これまで胃がん検診においては長い間、胃エックス線検査が推奨され行われてきました。一度でも受けたことのある方はお分かりだと思いますが、バリウムという白い液体を飲んだのちに、検査台の上でゴロゴロと体位を変え、レントゲン写真を撮っていく検査です。胃癌による死亡率を減少させるというしっかりとした科学的根拠もあるのすが、バリウムを飲んだあとお腹が痛くなる、検診を受ける日・場所などが限定される、要精査になる(検診でひっかかる)と再び胃カメラを飲まなければいけないなど、不満の声の多い検診の一つです。
このようななか、胃カメラによる胃がん検診の導入を望む声はかなり以前よりありました。しかし、当時は科学的根拠が少ないことから長らく先送りとなっていました。ところが近年、国内外の研究から胃内視鏡検診が胃癌の死亡率を下げるという根拠が徐々に示されるようになり、平成27年に厚生労働省「がん検診のあり方に関する検討会」より胃がん検診の検査項目は「胃エックス線もしくは胃内視鏡とする」との提言がなされました。これを受け全国の市民検診で胃内視鏡検診が徐々に導入され、仙台市でも平成31年度より開始されることとなりました。
胃カメラによる胃がん検診は、お近くの登録医療機関(診療所・病院)で受けることができますので利便性は向上すると思います。異常が発見された場合はその場で病変を採取し、精密診断をすることもできます。胃エックス線検査よりも胃癌による死亡率を下げる可能性があるのではないかというデータも出揃いつつあります。
胃カメラは一般的に偶発症(被検者の望んでいない事象)の極めて少ない安全な検査なのですが、残念ながら決して楽な検査ではありません。市民検診では比較的苦痛が少ないと言われている経鼻内視鏡は選択可能です。しかし、当院を含む多くの病院・診療所などで行われている鎮静剤・麻酔薬を使用しての胃内視鏡(いわゆる眠ってする内視鏡)は市民検診ではできません。何故ならこれらの薬剤を使用した胃内視鏡は、万全の対策を講じて実施しても明らかに偶発症の頻度が上昇するということが学会等の全国調査で知られており、「安全な検査方法でがんを早期発見する」という市民検診の基本理念に反するものであるからです。但し、「少々のリスクはあっても苦痛なく検査を受けたい」という、個人の判断も尊重されるべきであると思います。このような方々には、市民検診ではなく個人検診での鎮静剤・麻酔薬を使用した胃内視鏡をお勧めします。
胃エックス線検査と胃内視鏡検査はそれぞれ良い点、悪い点ともにあり、現時点では優劣を判断し難いのですが、胃がん検診の選択肢が増えたことは素晴らしいことだと思います。胃内視鏡検診のスタートを契機に胃がん検診の受診率が向上し、胃がんの早期発見・早期治療につながることを期待したいと思います。
苦しくない胃カメラをめざし、最新の細径内視鏡を導入しました!
2021.05.10

胃カメラは口や鼻から内視鏡を挿入して観察し、胃癌・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃炎・逆流性食道炎・食道癌といった病気がないか調べる検査です。2016年の国の指針で胃がん検診においても胃カメラが推奨され、より身近な検査となりました。しかし、残念ながら未だ決して楽な検査とはいえないのが現状です。
そのような中で近年、胃カメラの苦痛を軽減するため、細径内視鏡(通常内視鏡より細い内視鏡)を用いた経鼻内視鏡(鼻からの胃カメラ)や経口内視鏡(口からの胃カメラ)のニーズが高まっています。しかし、従来の細径内視鏡では技術的な限界から、その画質は通常内視鏡に比べ劣るものであり、内視鏡の細径化と高画質化の両立が長年の課題とされていました。
角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では、この度、主に経鼻内視鏡で使用していた細径内視鏡を従来のオリンパス社製EVIS LUCERA ELITE ® OLYMPUS GIF-XP290Nから同社の最新機種であるOLYMPUS®GIF-1200Nに更新しました。今回、導入した細径内視鏡はこれまでの細さ5.4mmの極細を維持しつつ、ハイビジョン画像を実現しています。その画質は、当院がこれまで経口内視鏡で使用していた太さ8.9mmの通常内視鏡(EVIS LUCERA ELITE ® OLYMPUS GIF-H290)と比較しても遜色はありません。よって、今回導入した細径内視鏡は経口内視鏡・経鼻内視鏡の区別なく使用可能であり、どちらにおいても検査の精度向上と苦痛低減が期待できます。
角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では今後も引き続き「苦痛の少ない」「安全で」「正確な」内視鏡検査をめざします。
【新しくなったの細径内視鏡の特徴】
|精度の高い検査の実現
・新型イメージセンサーの搭載とオリンパス社がこれまで培ってきた細径内視鏡の組み立て技術により、5.4mmの極細を維持しつつ、これまので細径内視鏡では実現できなかった明るく、ノイズの少ないハイビジョン画像が得られるようになりました。当院で新たに導入した最新の内視鏡システム(EVIS X1)と組み合わせて使用することにより、その威力はさらに向上し、より微細な血管や粘膜の構造がとらえられるようになり病気の早期発見に貢献します。
|苦しくない胃カメラのために
・5.4mmの極細の胃カメラは挿入時の鼻の痛みや咽頭反射(いわゆる胃カメラのときの「オェ!」)の軽減に役立ちます。
・従来の細径内視鏡と比較し先端部により柔らかい素材を使用していますので、挿入時の苦痛軽減が期待できます。
・従来の細径内視鏡では細いがうえに「こし」が弱く、胃の奥の十二指腸の挿入に難渋することがありました。新しい細径内視鏡ではこの部分を改良調整しております。
胃痛、胃のもたれ、吐き気、黒い便など気になる症状が続く場合は心配なさらずに是非ご相談ください。胃内視鏡検査(胃カメラ検査)について詳しくは下記をご覧ください。
まつだクリニックではオンライン診療を受けられます。
2021.04.02

仙台市若林区六丁の目の内科・消化器内科、角田記念まつだクリニックです。当院で行っておりますオンライン診療について、そのメリットや流れについてご案内いたします。
|オンライン診療とは
スマートフォンやパソコンを接続して、クリニックの予約・問診・診察・処方・決済をインターネット上で行うサービスです。
|オンライン診療のメリット
次のような患者さまで定期的な通院が必要な場合、無理なく治療を続けられる様に負担を軽減する選択肢となりえます。
・病院が遠方にあり通院するのは負担が大きい方
・日中が忙しく移動時間や待ち時間を確保するのが困難な方
・感染症の流行している中での通院が不安な方
|オンライン診療でできること
・いつもの先生の診察を通院せずに受けられるから、交通費や移動時間がゼロ
・スケジュール通りにスムーズに診察してもらえるから、忙しい方も便利
・その場で決済、処方せんや薬も届けてもらえるので、会計やお薬の待ち時間もゼロ
|当院のオンライン診療のポリシー
・初診は原則として対面での診療を行います。患者さまからご要望があり、担当医が病状が安定しオンライン診療が可能と判断した場合に開始となります。
・オンライン診療は、触診等を行うことができない等の理由により、得られる情報が限られています。そのため初診以後も、同一の医師による対面診療を適切に組み合わせて行うことが、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で求められています。よって、新たな症状に対しては原則対面での診察を行います。また、病状が安定していても、原則約3か月に1回は対面での診察を行います。
|オンライン診療の流れ
①必要な情報を確認
当院ではオンライン診療サービス(クロン)を利用しています。オンライン診療を希望される患者さまは医師もしくはスタッフにご相談ください。アプリのダウンロード方法、予約の際に必要な「医療機関コード」をお教えします。
↓
②診療を予約、問診回答
クロンにアクセスし、医療機関コードを入力してください。診療を予約し、問診に回答してください。
↓
③ビデオ通話で診察
予約時間になりましたら医師から着信があります。
↓
④クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners対応)で決済する
下記の費用が決済されます。
・診察代金
・情報通信機器の運用に要する費用 500円
・クロンアプリ利用料330円
・処方箋を薬局へ郵送する場合の切手代
↓
⑤薬/処方箋が届く
いかがでしょうか?ご来院時に医師やスタッフより「医療機関コード」をお伝えする仕組みとなっておりますので、プライバシーに関しても安心してご利用いただけます。仙台、宮城、東北の患者さまにご利用いただき、受診の負担軽減につなげられることを願っております。
オンライン診療は下記よりご利用ください。
より苦しくない大腸カメラ・胃カメラ検査へ。最新の内視鏡システムを導入しました!
2021.03.19

角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では、大腸内視鏡や胃カメラで使用する内視鏡システムを従来のオリンパス社製「EVIS LUCERA ELITE」から同社の最新・最上位機種である「EVIS X1」に更新いたしました。今回導入した内視鏡システムでは下記のようなオリンパス社独自の最新テクノロジーが搭載されており、「内視鏡検査の苦痛軽減」、「病気の早期発見」、「病気の正確な診断」、「治療での安全性向上」が期待できます。
角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では今後も引き続き「苦痛の少ない」「安全で」「正確な」内視鏡検査をめざします。
【新しくなった内視鏡システムの特徴】
|苦痛のない検査のために
・EDOF(Extended Depth of Field)
これまでのシステムでは心臓の拍動や胃腸の蠕動がある状況下でピントを合わせ内視鏡写真を撮影することは医師にとって大きなストレスでした。EDOFは近点と遠点のそれぞれにピントを合わせた2つの画像を合成することで、広範囲にピントのあった写真をつくる新技術です。ワンタッチで「簡便」に「質の高い」画像が得られるため、写真の撮りなおしが減り検査時間の短縮が期待できます。
|病気の早期発見のために
・TXI(Texture and Color Enhancement Imaging)
内視鏡画像の微妙な変化を指摘し胃がんや大腸がんを発見するには医師の経験と勘が必要でした。TXIは「わずかな色調の変化を分かりやすく」「わずかな凹凸の変化を捉えやすく」「暗い部分を明るく」画像処理する新技術です。画像上のわずかな変化に対する視認性が向上し、病変の早期発見に貢献します。
|病気の正確な診断のために
・NBI(Narrow Band Imaging)
従来の内視鏡システムにも搭載されています。ヘモグロビンに強く吸収される特殊な波長の光をあてて粘膜表層の血管走行や微細構造を強調する技術です。これまでの豊富なエビデンスの蓄積もあり、今や内視鏡診断のゴールデンスタンダートとなっています。
|安全な治療のために
・RDI(Red Dichromatic Imaging)
RDIは特殊な波長の光を用いることで組織の深い部分のコントラストを形成する新技術です。深部血管や出血時の血液の観察がしやくすなり、内視鏡手術での迅速な処置や手技をサポートします。
角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では、「苦しくない」「痛くない」「安全で」「正確な」大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)、胃内視鏡検査(胃カメラ検査)を行えるように常に最先端の機器や技術を取り入れています。便秘、下痢、腹痛、血便など気になる症状が続く場合は心配なさらずに是非ご相談ください。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)、胃内視鏡検査(胃カメラ検査)について詳しくは下記をご覧ください。
B型肝炎と肝炎治療実施医療機関の役割について(その1)
2020.05.10

B型肝炎・C型肝炎はウィルスの感染により発病し、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんといった重篤な病気を発症する恐れがあります。国内の感染者数はB型肝炎が約120万人(2011年)、C型肝炎が約200万人(2008年)と推定されています。国はB型肝炎・C型肝炎を国内最大の感染症と認識し、肝炎の早期発見、医療機関へのアクセス、肝炎の正しい知識の啓蒙など様々な課題の改善を目的として肝炎対策特別事業を展開しています。当院はこの事業における肝炎治療指定医療機関に指定されています。今回はB型肝炎・C型肝炎治療と肝炎治療指定医療機関の役割に関して、2回に分けてお話ししたいと思います。
・高額なB型肝炎治療薬と医療費助成制度
近年の肝炎治療の進歩は目覚ましいものがあります。1980年代以降B型肝炎の治療ではインターフェロンが可能となりましたが、注射薬であること、副作用、有効率の低さから治療可能な患者さまは限定的でした。2000年以降ウィルスの増殖を抑制する核酸アナログという飲み薬が次々に登場し、副作用も少なく確実に肝炎を鎮静化できることから、多くの患者さまがこの治療薬の対象となりました。しかしながら、製薬会社の長年の研究努力によりこのような素晴らしい薬が創薬されたのですが、その対価としての薬価は決して安くはありません。例えば最新の核酸アナログであるベムリディーは1錠997円です。1日1錠を毎日内服しなければならないので、月のお薬代は約3万円になります。核酸アナログはウィルスの増殖を抑制する薬であり、完全に消失させるわけではありません。よって、基本的には生涯内服を続けなければいけない薬であり、その患者さまの経済的負担は計り知れません。肝炎対策特別事業ではこの高額な治療費をサポートする医療費助成制度があり、これにより多くの患者さまが経済的な不安を感じずに治療を受けられるようになりました。
肝炎治療で医療費の助成を受けるには診断書作成指定病院(県内では21施設が指定されています)の肝臓専門医・消化器病専門医に診断書を作成してもらい、申請する必要があります。助成が認可されれば、以後は当院のような治療実施指定病院(県内では約230施設が指定されています)でも治療を受けることができます。
・医療費助成の手続きの簡素化と通院負担軽減の可能性
B型肝炎の治療に有効な核酸アナログはこれまで5種類が発売されました。ゼフィックス(一般名:ラミブジン)という初期の核酸アナログでは耐性(薬が効かない)ウィルスが高頻度に出現することが問題でした。また、耐性ウィルスの出現時は専門的な知識による対応が必要でした。次に発売されたヘプセラ(一般名:アデホビル)は、ゼフィックスほどではありませんがやはり耐性ウィルスの懸念があり、それだけではなく長期の服用による副作用にも注意を払う必要がある核酸アナログでした。しかしながら、2006年に発売されたバラクルード(一般名:エンテカビル)は耐性ウィルスの出現や副作用の心配が少ない核酸アナログで、以後、安心して治療できるようなりました。2017年にはベムリディー(一般名:テノホビルアラナフナミドフマル酸塩~少々長いので我々専門医はTAFと言っています)という核酸アナログが発売されました。これは、2014年に発売されたテノゼット(一般名:テノホビル)を改良したもので、耐性ウィルスの出現率は極めて低く、またテノゼットの課題であった長期内服による副作用を大幅に軽減した、非常に優れた核酸アナログです。
これまで医療費助成で核酸アナログの治療を続けるには、毎年、診断書作成指定病院の医師に更新のための診断書を作成してもらう必要がありました。これはB型肝炎の患者さまにとって大きな負担であったと思います。以前、私は青森県の八戸市立市民病院(医療圏30万人の中核病院)に勤務していました。その地域の診断書作成病院の一つであったため、毎年春には60人くらいの核酸アナログの医療費助成更新の診断書を作成していました。バラクルードが使用できるようになってからのB型肝炎治療は素晴らしく、耐性ウィルスや副作用の心配がほぼなくなりました。青森県は広大な地域です。検査と薬の処方のために遠方から何時間もかけて通院されている患者さまも多くいて、負担軽減のためクリニックとの病診連携を常に模索していました。平成27年よりB型肝炎の核酸アナログ治療では医療費助成の手続きが簡素化され、これまで必要であった更新のための医師の診断書が不要となりました。これにより利便性の高い近隣の治療実施指定病院でより治療が受けやすい環境が整ったと思います。
B型肝炎は早期に発見し、医療機関や助成制度を上手に利用すれば、治療薬の進歩もあり、多くの患者さまが健康な人と変わらない生活を送れるようになりました。しかし、残念ながら未だウィルスを完全に体内から排除することは難しく、長期にわたる核酸アナログの内服が必要な病気です。当院は肝炎治療医療機関としてB型肝炎の「真の完治」の日がくるまで、患者さまと向き合いながら健康をサポートしていきます。
次回はC型肝炎と肝炎治療実施医療機関の役割についてお話しします。
難病指定医について
2018.12.03

当院は消化器疾患領域の難病指定医療機関に認定されています。難病指定医なんて聞いたことがないと言われる方が多いと思いますので、少し難病指定医の役割についてお話ししたいと思います。
まず「難病」という言葉はいつ頃から用いられるようになったのでしょうか?人は皆いつか病気になってしまいます。科学の未発達時代には多くの病気が克服できなかったと思います。「不治の病」の定義はその時代の医療や社会の事情により変わるものです。国が初めて「難病」を認識し対策を講じたのは、スモン(亜急性脊髄神経症)という病気だったそうです。昭和30年頃に流行した下半身の麻痺や視力障害をきたす原因不明の病気でした。患者の多い地域の地名から「釧路病」とも言われ、当初はその地域に土着するウィルスが原因の風土病ではないかと考えられていました。しかし、患者数の増加に伴い国はこの原因不明の病気に対し早急に研究班を設立し、大規模な疫学調査を行い、「キノホルム」という整腸剤が原因であることを突き止めました。キノホルムの発売が中止されてから患者は激減したそうです。この経験から我が国は、例え難病と言われている病気であっても、国家の総力を結集し研究を行えば、その原因が解明されるかもしれないという教訓を得ました。国は昭和47年に難病対策要綱を策定し、難治性肝疾患をはじめ8疾患を研究対象として選定し、そのうち4疾患を医療費の助成対象としました。その後、約半世紀が経過し社会保障制度の変化、患者数の増加、予算確保などの荒波に揉まれながらも、平成30年には331疾患が指定難病となっています。
難病指定医の役割は2つあります。一つは患者様が難病にかかっていること及びその病気の程度を診断し、証明書を作成することです。これは、難病の疫学調査や医療費助成の診断書として利用されます。もう一つは患者様に対して、難病に関する情報を提供することです。よって、指定医には、対象となる難病の診断・治療に5年以上の経験もしくは専門医資格が必要です。私の場合は、仙台医療センターや東北大学病院で7年間、難治性肝疾患診療のトレーニングを受け、消化器病専門医、肝臓専門医の資格取得後、平成20年に難病指定医(消化器領域)の認定を受けました。
難病というと「希少な疾患」というイメージを持つかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。肝臓専門医は、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性肝硬変(原発性胆汁性胆管炎)といった指定難病は比較的よく遭遇する病気です。私は平成20年から27年まで青森県の八戸市立市民病院(医療圏30万人の地方中核病院)に勤務していました。勤務当初はその地域では唯一の肝臓専門医でした。この7年間に、私は肝生検で28人の原発性胆汁性肝硬変、34人の自己免疫性肝炎の患者様の確定診断を行いました。原発性胆汁性肝硬変には、抗ミトコンドリア抗体という血液検査で分かる強力な診断マーカーがあるため、肝生検を行わないで診断ができる場合があります。また、ご高齢の患者様や状態の悪い患者様は肝生検ができません。診断確定後に他医から引き継いだ患者様もおり、実際診療にあたった患者様は110人くらいにのぼります。
原発性胆汁性肝硬変は国の疫学調査で分かっている患者数だけでも約2万人です。調査に参加してない患者様もいるので、実際にはもっと多く罹患しているはずです。自己免疫性肝炎は、最近やっと疫学調査の対象となったため現在患者数は不明ですが、国は1万人程度を想定しているようです。よって、原発性胆汁性肝硬変や自己免疫性肝炎といった指定難病は決して「稀な」な病気ではないのです。
難病というと「不治の病」=(イコール)「死」を連想するかもしれません。しかし、必ずしもそうではありません。例えば、原発性胆汁性肝硬変では、ウルソデオキシコール酸という安価で安全性の高い薬の内服でほとんどの患者様は病状が安定します。病気が進行して症状が出現するのは10人に1人です。その中で、肝臓が全く機能しなくなるまで進行し、肝移植の考慮にまで至るのは10人に1人と言われています。自己免疫性肝炎の場合も免疫を調整する薬で安定する患者様が多いです。軽症例では、前述のウルソデオキシコール酸のみでコントロールできる場合もあります。残念ながら、どちらの病気も現時点で「完治」というのは難しいですが、早期に診断し、きっちりと治療を行えば、ほとんどの患者様が健康な人と変わらない生活を送ることができるのです。
難病指定医は、長い航海の「水先案内人」のようなものです。病気に関する知識と経験を生かし、様々な不安を抱える指定難病の患者様が平穏な日常を過ごせるよう導くのが我々の仕事です。いつか病気が克服される日が来ると信じて、患者様と日々向き合っていきます。
